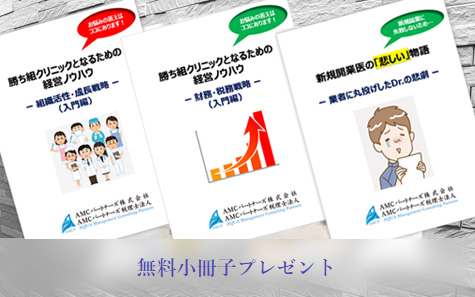離婚は人生の大きな転機です。日本の離婚件数自体は平成14年以降、減少傾向が続いていますが、熟年離婚だけは高止まりが続いており、人生の後半、夫婦別々に人生設計をしなおすケースが増えています。
今号では、そんな人生の転機にかかる税金について考えていきます。
1.財産分与・慰謝料
まずは財産分与・慰謝料についてですが、原則どちらも税金はかかりません。
財産分与は夫婦が共同で築いた財産を分け合うものであり、どちらか一方からの贈与ではないので、贈与税の対象外です。
また、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金であるため、こちらも所得税や贈与税はかかりません。
ただし、一部例外的に税金がかかるケースもあります。
それは、金額が多すぎる場合です。
財産分与の割合は、原則1/2ずつです(個別事情を加味して多少前後する分には構いません)。そのため、どちらか一方の取り分が過度に多い場合、本来の自分の取り分からの「贈与」である、とみなされて贈与税が課されることがあります。
その他、よくあるのが自宅を配偶者に渡したケースで、共有財産に占める自宅の価値の割合が高い(現預金等で双方の割合を調整できないほど)場合には、贈与税の対象となる可能性があります。
また、慰謝料についても、社会通念上高額すぎる場合には、贈与税が課されることがあります。
慰謝料は、離婚事由や支払能力、婚姻期間等に応じて変動しますが、相場としては300~500万円程度が上限ですので、それを大きく超える場合には課税される可能性が出てきます。
2.養育費
養育費は、子どもへの扶養義務(生活費・教育費)の履行として支払われるものであり、原則として課税はされません。ただし、次のような場合には贈与税が課される恐れがあります。
①一括して受け取った場合
元夫婦双方の合意が必要ですが、養育費は一括払いが可能です。
ただし、養育費は「必要なときに必要な額」を請求するのが原則で、贈与税においても「生活費や教育費」として非課税とされるのは、「通常必要と認められる」その都度の金額であり、将来要すると見込まれる分をまとめて受取った場合には贈与とみなされる可能性があります。この場合、受け取った金額のうち通常必要と認められる金額を超える部分から110万円の基礎控除を引いた金額に対して贈与税が課されます。
どうしても一括で授受したい場合、「教育資金贈与信託(1,500万円まで非課税)」のご利用を検討された方が良いでしょう。
②使わずに貯金している場合等
子どもの将来のために…というのはわかりますが、養育費は子どもの生活費・教育費に充てられる必要があります。
単に資産形成のための貯金や投資に充てた場合、目的外使用として贈与税が課される恐れがあります(貯金理由が「将来の学費」であれば問題ないようですが、事前に協議して取り決めを行う方が賢明です)。
③金額が過大な場合
養育費は親の収入や子の年齢・人数などを元に「養育費算定表」を目安に算定されますが、これを大幅に超える場合には、贈与税が課される恐れがあります。
ちなみに親が高所得者(年収2,000万円超)の場合、表の上限を超えてしまいますが、その場合は上限で頭打ちとする場合が多いようです(収入に連動して子どもの生活費・教育費が青天井で増える訳ではないので)。
3.分与財産で所得税がかかるケース
共有財産のうちに不動産や有価証券、宝石・貴金属など、含み益が生じる財産がある場合、財産分与により所得税がかかる場合があります。それは、自分名義の財産(多いのが自宅)を相手に渡す場合です(財産を時価で換金して分与したものと考え、譲渡所得が生じます)。
とはいえ、自宅に関しては次の特例のおかげでほぼ所得税はかかりません。
(1)譲渡所得の特別控除が使える
離婚後の元妻への自宅の財産分与には、「居住用財産の譲渡の特別控除」が使えます(相手が第三者=戸籍上「他人」であることが要件のため)。要件は以下の通りで、確定申告をすることで適用が可能です。
・夫婦で暮らしていた自宅である(離婚前に別居していた場合は、自身が住まなくなった日から3年以内)
・離婚後に譲渡する
・他の特別控除の適用を受けていない
これにより、自宅の譲渡に係る所得(利益)が「自宅の時価-取得価額-譲渡に係る経費-特別控除3,000万円」となります。つまり、時価が購入価額より高く、更に含み益が3,000万円以上ないと課税されないのです。
ちなみに10年超住んでいた場合には所得税率の軽減規定もあります。
(2)不動産取得税がかかる
不動産取得税は「新たに取得」した不動産に課される税金です。
そのため、いずれか一方の名義で購入した自宅を財産分与により相手に渡した場合、原則的には課税対象なのですが実質的には共有財産の分配であるとして、裁量により不動産取得税の非課税としている自治体が多いです。
ただし、慰謝料の支払いとして自宅を譲った場合や、前述のように一方に過大な分与が行われた場合には、新規取得として課税されることがあります。
(3)登録免許税
登録免許税は登記という行政サービスに対する手数料です。
そのため、これに関しては、原則通り1/2ずつ財産分与をしたとしても、元々が自分の名義でなかった場合、名義変更登記により課税されます。
税額は固定資産税評価額の2%で、高額となるケースもあるため移転登記を行わずに離婚するケースが散見されますが、売却や相続などの際に後々に問題化することが予想されますので、適切なタイミングでの名義変更をお勧めいたします。
4.年金分割
近年の離婚で必ず考慮しなければならないのが「年金分割」です。
ご存じの方も多いと思いますが、結婚期間中の夫の厚生年金(国民年金は対象外)について、1/2を妻の取り分とする制度です。熟年離婚の増加を受けて制定された制度で、従来、厚生年金が夫の総取りだったことで離婚後の配偶者の経済的な自立が困難であることが社会問題となり導入されました。
なお、厳密には協議の上で行う「合意分割」と、自動的に1/2が分割される(手続きは必要)「3号分割」の2種類があります。
「合意分割」は、結婚期間中の夫婦の厚生年金(なので2人とも加入していた場合は2人の厚生年金の合計)を1/2を上限として協議のもと分割する制度です(殆どの場合1/2になります)。
一方、「3号分割」は、妻が専業主婦(国民年金の第3号被保険者)だった場合に、1/2を自動的に妻の取り分とする制度です。
そして肝心の税金についてですが、結論として贈与税はかかりません。
上述の通り、制度上1/2が上限=原則通りの配分割合を超えて渡すことが出来ないため、制度の仕組み的に贈与税がかかることはないのです。