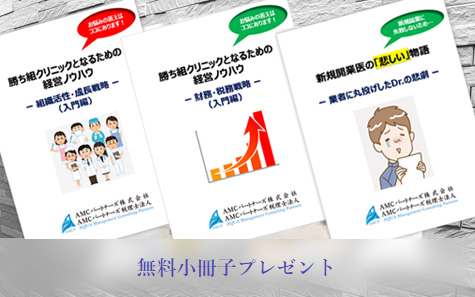今号では、知ってはいるけれど今ひとつ曖昧、といった相続税法上の非課税・軽減規定のうち、主たるものについて簡潔に要点をまとめて整理していこうと思います。
1.基礎控除
最初に、相続税の基礎控除についてです。
「3,000万円+600万円☓法定相続人の数」が、相続した財産の総額から控除されます。
相続財産が基礎控除額以下だった場合は申告不要です。
とはいえ、10年前(H27年)に控除額が減額(改正前「5,000万円+1,000万円☓法定相続人の数」)されて以降、いまや約10人に1人が相続税の課税対象となる時代です。基本的には相続税ありきでご準備いただくのが望ましいでしょう。
なお、法定相続人とは「配偶者(常に)+子→孫→父母→兄弟姉妹の優位順で先順位の相続人」のことを指します。
例えば、配偶者と子がいる場合はその人数で、以降は数えません。養子は実子がいれば1人、いない場合は2人までカウントされます。そのため、孫を養子にして法定相続人の数を増やすのは、相続税対策の常套手段になります。
また、相続を放棄した場合、その放棄がなかったものとして、法定相続人の数に数えられます(後順位の相続人の方が多いから、自分は放棄して法定相続人を増やそう、ということは出来ません)。
2.生命保険金の非課税
相続税法上、生命保険金には、「法定相続人の数☓500万円」の非課税枠が設けられています。
1人毎ではなく、全体での非課税枠ですので、例えば法定相続人5人で2,500万円の非課税枠がある場合、うち1人だけが2,000万円の保険を受け取ったとしても全額非課税となります。
ちなみに相続を放棄した場合、上述の通り法定相続人の人数の計算には含まれるのですが、本人は非課税の適用を受けることはできません(生命保険は遺産分割とは別の契約で受取人を指定できるため、たとえ相続を放棄していても受取ること自体は可能です)。
また、相続税の対象となる生命保険は、亡くなった方が契約者(保険料負担者)かつ被保険者で、受取人が相続人である契約です。契約内容によっては所得税や贈与税の対象となる場合もありますので、事前にご確認ください(今回は詳細を省きますが)。
なお、相続人以外が受取人(子を飛ばして孫を受取人にした場合等)の場合、この非課税枠は適用されませんのでご注意ください。
最後に、類似の非課税規定で「死亡退職金の非課税」がありますが、対象が死亡退職金に代わるだけで、内容的には生命保険金の非課税とほぼ同じです(非課税枠も同じ)。
3.小規模宅地等の特例
不動産は相続財産の30~40%を占める主要財産であり、相続人の生活基盤ともなる重要な資産です。
そのため、一定の土地等については、相続人の生活保障のため、相続税の評価額を大幅に減額する特例が設けられています。具体的には次の通りです。
(1)特定居住用宅地等(自宅の土地)
・減額割合:80%(20%だけ課税対象)
・限度面積:330㎡(約100坪、超えた部分は減額されない)
・要件:亡くなった方の自宅の土地で、配偶者又は同居の親族が申告期限(亡くなった時から10ヶ月)まで所有し住み続けている。但し、配偶者と同居親族がいない場合に限り、別居で自宅がない(過去3年間)親族が取得しても適用あり。
(2)特定事業用宅地等(事業所の土地)
・減額割合:80%
・限度面積:400㎡(約120坪)
・要件:亡くなった方が事業に使っていた土地で、取得した相続人が申告期限までその事業を継続し、土地を所有している。
なお、類似の規定に「特定同族会社事業用宅地等」というものがあり、こちらは特定同族会社(亡くなった方とその親族の持分が50%超の法人)に、亡くなった方が貸していた土地について、同様の減額を受けられる規定ですが、先に述べた通り「持分」が判定基準のため、“持分の定めない医療法人”は適用対象外となります。
(3)貸付事業用宅地等(アパートや貸家の土地)
・減額割合:50%
・限度面積:200㎡(約60坪)
・要件:アパートなどの賃貸に使っていた土地で、取得した相続人が申告期限まで賃貸事業を継続し、土地を所有している。
ちなみに、駆け込みで不動産を賃貸化して減額規定を受けるケースが横行したため、R3年4月以降、亡くなった時より3年超前から賃貸を行っていない土地は対象外となりました。
4.配偶者の税額軽減
相続財産は配偶者との共有財産的な性格があること、また、相続後の配偶者の生活保障などの観点などから、相続税では「配偶者の税額軽減」という非常に大きな減額規定が設けられています。
具体的には、配偶者が取得した財産については、1.6億円か、1/2のいずれか「多い」金額が控除されます(つまり、最低でも1.6億円まで相続税がかかりません)。
非常に大きな軽減措置ですので、「ひとまず配偶者の名義に」となるケースも多いのですが、二次相続(配偶者から子や孫への相続)を考慮すると、必ずしも得策とは言えないケースもあります(既に配偶者も多額の財産を保有している場合等)。
相続税は累進課税といって、一度に取得する財産が多いほど税率が高くなる仕組みです。基本的には、下の世代に細かく財産を移転した方が最終的な税負担は抑えられる傾向にありますので、財産分与の際には、将来の二次相続まで含めた総合的な税負担まで織り込んで計画する必要があります。
なお、注意すべき点として、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」は、相続税の確定申告を行うことが適用要件です。くれぐれも申告漏れだけは無いよう、ご留意ください。