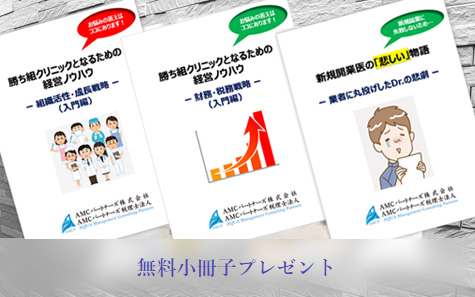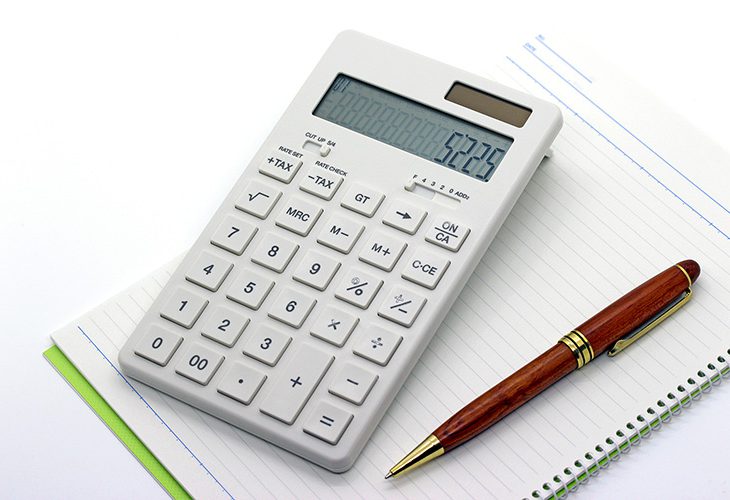今号では、6月13日に可決・成立した年金改革法から、特に事業者や従業員にとって影響のある改正点と、7月1日に国税庁より公表された「令和7年分路線価」の概要ついて、解説してまいります。
1.「106万円の壁」撤廃
社会保険の加入要件のうち「106万円の壁」が撤廃されます。
現在、被保険者数51名以上の企業については、次の要件を満たした場合に社会保険の加入義務が生じます。
①月の収入が8万円以上(年収約106万円)
②週の所定労働時間が20時間以上(雇用契約書で判断)
③学生でない
④2ヶ月超の雇用見込み
このうち、①の賃金要件が令和8年10月に撤廃される予定です。
現在の最低賃金(全国平均)で週20時間働いた場合、年収は約109万円となるため実質的に形骸化しており、また、今後続くであろう最低賃金の引き上げを考慮すると、働き控えを助長するおそれもあるためです。
ただし、「20時間の壁」は残るため、今後もこれを意識した20時間未満での雇用契約による働き控えは残るものと考えられ、人手不足の根本的解決には繋がらないとの見方が一般的です。
2.企業規模要件の撤廃
社会保険の企業規模要件(被保険者数による判定)が段階的に縮小・撤廃される予定です。
現行の50人超から10年かけて徐々に基準となる人数を減らしていき、最終的には令和17年10月に完全撤廃される予定です。
具体的には、
・令和9年10月~:35人超
・令和11年10月~:20人超
・令和14年10月~:10人超
・令和17年10月~:企業規模要件撤廃
となる予定です。
上述の「106万円の壁撤廃」と合わせると、将来的には企業規模に関わらず、週20時間以上勤務であれば社会保険の加入義務が生じることになります(学生の場合等を除く)。
3.在職老齢年金の減額基準の見直し
給与と年金の合計が基準額を超えた場合に、厚生年金の一部が支給停止となる基準の金額が50万円から62万円に段階的に引き上げられます(基準金額を超えた額の1/2が支給停止)。
これは、高齢者の働き控えを抑止するためで、62万円は「50代の平均的賃金+年金の額」として設定された金額です。
令和7年は51万円、令和8年に62万円へと引き上げられる予定です(賃金変動に応じて改定の可能性あり)。これにより、シニアワーカーのうち、新たに20万人が老齢厚生年金を全額受給できるようになる見込みです。
なお、基礎年金は収入に関係なく支給されるので今回の改正には関係ありません。
4.厚生年金保険料の上限の引き上げ
高所得者の厚生年金保険料が引き上げられます。
厳密に言えば、「標準報酬月額」という社会保険料を決める基準(例:月額給与が◯◯万円以上~◯◯万円未満なら月額保険料は◯◯円といった基準)について、厚生年金保険料に係わる上限月額が令和9年9月から3年かけて、現在の65万円⇒75万円へと段階的に引き上げられます。
これにより、増加する保険料負担額は以下の通りです。
| 開始時期 | 上限月額 | 保険料増加額 |
| 令和9.9月~ | 68万円 | +約2,700円/月 |
| 令和10.9月~ | 71万円 | +約5,500円/月 |
| 令和11.9月~ | 75万円 | +約9,100円/月 |
(※増加額は現在の保険料との差額)
なお、会社負担分も含めると総負担額は上記の倍額になるため、最大で年間22万円弱の負担増となります。
5.私的年金制度の拡充
iDeCoや企業型DCなどの私的年金制度について、より幅広い範囲の人が加入できるよう下記の改正がなされました。
①iDeCo加入可能年齢の上限が65歳未満から70歳未満に引き上げ
②企業型DCのマッチング拠出(従業員自身が会社の拠出する掛金に上乗せして負担する方法)について、会社の拠出する掛金を超える金額を拠出できるように変更
③各社の企業年金の運営状況を厚生労働省がまとめて公表、自社と他社との比較や運用成績の分析を行えるように
6.令和7年分路線価
今月1日、国税庁より、令和7年分の路線価が公表されました。
路線価とは、毎年1月1日時点の1㎡当たりの土地の評価額で、公示地価の概ね8割を目安に定められており、贈与税や相続税の土地の評価の際に用いられます。
今年の路線価の概要は以下の通りです。
(1)全国的に地価上昇が継続・拡大
全国平均は4年連続の上昇となりました。
全国の標準宅地(地域ごとの標準的な宅地)の平均は、対前年比で2.7%上昇し(3月に公表された公示地価の全国平均が2.7%上昇でしたので、それをそのまま反映したかたち)、これはバブル期以降で最大の伸び率となっています。
(2)地方も堅調
三大都市圏(東京・大阪・名古屋)や地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)は、地域差はあるものの、いずれも4年連続の上昇、その他の地域でも上昇傾向が継続しています。
インバウンド需要の回復や、都市部の物件価格高騰、各地の駅前再開発などで、今後も上昇基調が続くことが予想されます。
ただし、地価の上昇はイコールで税負担の増加にも繋がりますので、一概に歓迎すべき話題というわけでもありませんが…。