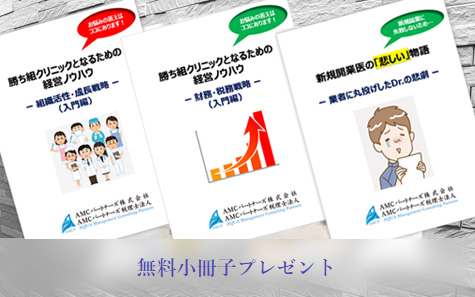今号では、ご質問を頂くことが多い「研修費等の課税関係」についてまとめて解説して参ります。
1.研修費等の課税関係
法人の役員や従業員の研修費・資格取得費・学費などを法人が負担することがありますが、その際に気になるのは、下記2点です。
①事業経費にできるのか
②給与課税はされないか(※個人事業主本人分は否認されても私費になるだけですが)
そのための税法上の要件をまとめると次のようになります。
・役員又は従業員を対象としたものである
・職務に直接必要な技術・知識の習得や免許・資格の取得費用
・上記の為の研修会・講演会等の出席費用、大学等の聴講費用
・上記のうち金額が適切なもの
いざ羅列してみると当然な気もしますが、それぞれの要件について、気をつけるべきポイントを見ていきましょう。
(1)役員又は従業員を対象としている
事業に関係のない家族や友人の研修費等を法人が負担すると、法人側では寄附金として一部が法人税の計算上経費否認、個人側でも一時所得として所得税がかかることになります。
(2)職務に直接必要な研修等である
自己啓発目的の研修費用などは、個人のモチベーションアップには寄与するかもしれませんが、事業の収益向上に直接結びつくものではないため、経費として認められません。
(3)金額が適切なもの
他の経費でもそうですが、不当に高額なものは経費となりません。
ただし具体的な金額基準があるわけではなく、高額なものであっても一般的な相場から乖離していなければ問題ありません。
なお、直接業務に必要な資格であっても、個人に帰属する資格の取得費用は経費にすることはできません。医師免許の取得にかかった学費などはこれに該当します。
2.研修費等の具体例
(1)研修費の範囲
研修費には、次のような費用が含まれます
・セミナー受講料、免許・資格取得のための講習会参加費
・受講のための交通費、宿泊費、食事代(高額でない)
・外部から招いた講師の謝礼金、交通費
・社内研修の会場費、資料作成費
・研修で使うテキスト代
ただし、セミナーや研修終了後の懇親会費は交際費となります。
また、研修旅費の名目であっても、
・同業者団体の主催する主に観光を目的とした団体旅行
・観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
などは研修費としては認められず、給与課税がされます。
(2)学資金
従業員の資格取得のため、専門学校や大学院の学費を学資金として支給することがありますが、こちらも次の要件を満たせば、研修費等として経費化が可能です。
①通常の給与に加算して支給すること(学資金が増えた分を給与から減額してはならない)
②対象者は従業員(役員や、役員・従業員の親族などは対象外)
③クリニックの業務遂行上必要なもの
3.過去の裁決事例
税務調査では特に“業務遂行上の必要性”が問題となりますが、国税不服審判所の過去の裁決より研修費が否認された事例をご紹介します(平成13年3月30日裁決)。
当該事例では、歯科医師が外国人患者対応・海外研修等のためとして計上していた英会話の授業料について否認がされました。納税者側は上記の理由から必要経費である旨を主張しましたが、実際の外国人患者数はごく少数であったこと、また、最新の医療知識の習得など業務遂行上ある程度の必要性はあるものの、英会話研修の全てが業務遂行上必要とは認められないとの判断から最終的には請求が棄却されています。
また、平成31年3月28日の裁決でも、ラジオ英会話教材が自己啓発教材の範疇であるとして請求が棄却されています。
研修費として計上するには、客観的に業務遂行上、直接必要な経費であることが必要となります。「間接的には有用」「ある程度の必要性はある」程度の内容の抗弁では上記のように否認される恐れがあるということです。
特に、役員の研修費が否認されて給与課税となった場合、「臨時的な役員への賞与」扱いとなり、法人税法上、経費として否認されるため、所得税のみならず、法人税まで追徴を受けることになります。
さらに、消費税計算が原則課税の場合、「研修費」としていたものが「役員賞与」と認定されることで消費税が控除できない(給与は不課税)こととなり、消費税の追徴も発生することになります。
なお、従業員を対象とした英会話については、
・従業員であれば全員自由に研修を受けられる
・社会通念上妥当な金額である
・社内規定に明記されている
といった要件を満たせば、研修費ではなく福利厚生費として経費化が認められることが多いようです。
4.実務上の留意点
研修費の経費計上には、実務上、下記の点をご留意ください。
①業務遂行上の関連性を説明できるようにしておく
②特定の人だけを対象とする場合の人選理由を明らかにする
③請求書等の他、参加者リスト等の証憑も用意しておく
④法人での経費化を意図した支出は法人名義で行う
⑤従業員が立替払いした研修代金の一部を法人負担として精算する場合には法人名義の領収証を回収する