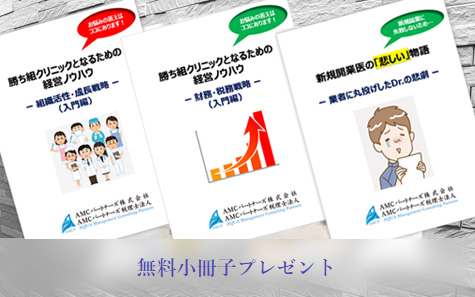令和7年の税制改正、及び令和8年に予定される社会保険制度改正により、いわゆる「年収の壁」に大きな変化が起こっています。今号では、それらを整理し、今後の「年収の壁」についてまとめていきたいと思います。
1.所得税
まずは最も複雑化した所得税から見ていきます。
(1)本人に納税義務が発生する 『160万円』
労働者本人に所得税の納税義務が発生するラインが「103万円」から「160万円」に引き上げられました。
そもそも何故103万円だったのか?という話ですが、基礎控除48万円と給与所得控除55万円、2つの控除を合わせて103万円までは税金がかからない、という仕組みになっていました。
今回、税制改正により基礎控除が48万円⇒58万円、給与所得控除が55万円⇒65万円に引き上げられました。
そこにさらに「特例加算額」という、基礎控除の加算枠が37万円追加され、3つ合わせて「160万円」まで所得税がかからないこととなったのです。
(2)扶養親族から外れる 『123万円』
次に家族などを扶養に入れられるかの収入ラインです。
改正前は本人に所得税がかかる収入と同じ「103万円」だったのですが、改正後は「123万円」になっています。
何故本人の課税ラインと違うのか?という話ですが、実は上述の「特例加算額」が加味されるのは本人の納税義務の判定のみで、扶養の判定では従来通り、基礎控除と給与所得控除だけが反映されるのです。
そのため、改正後の基礎控除58万円+給与所得控除65万円で「123万円」が扶養親族のラインとなり、本人に納税義務はないが扶養からは外れるというややこしい事態になっています。
(3)大学生の子供は 『150万円』まで満額控除
19歳~22歳の扶養親族がいる場合、特定扶養親族として、63万円の控除が受けられるのですが、前述の通り、従来はお子さんのアルバイト代が「103万円」を超えると扶養から外れてしまっていました。
これが、今回の改正により「特定親族特別控除」という新規定が創設され「150万円」までは満額控除(63万円)、以降も控除額は逓減(最低3万円)しますが、「188万円」までは扶養に含めることが可能になりました。
(4)その他の基準収入金額の変更
そのほかの所得控除の要件も次の通り変更となっています。
・配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる収入
改正前:150万円⇒改正後:160万円
・勤労学生控除(学生ご本人の控除)が受けられる収入
改正前:130万円⇒改正後:150万円
2.住民税
所得税の改正と連動し、住民税の課税ラインも「100万円」から「110万円」に引き上げられました(お住いの市町村によっては110万円以下でも課税される場合がありますのでご注意ください)。
これは住民税も給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられたためです(ただし、所得税と異なり基礎控除は据え置きとされたため、増加額は10万円に留まっています)。
なお、扶養に入るための収入要件は所得税と同じ123万円(住民税にも特定親族特別控除が創設されたため19歳~22歳は188万円まで)になるようです。
3.社会保険
(1)“106万円の壁”が撤廃(予定)
社会保険の加入義務要件のうち、“106万円の壁”が令和8年10月に撤廃される予定です。
こちらは所得税等とは逆に収入が減る内容の改正になります。
ご存知の通り、年収が106万円(月額8.8万円)を超えると社会保険への加入義務が生じるというものですが、これが撤廃=収入要件が無くなるため、週の勤務時間が20時間以上であれば社会保険の加入義務が生じることになります(学生等は除く)。
ただし、現状ではパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されているのは被保険者数が51人以上の事業者に限定されていますので、ただちに影響のあるクリニックは少ないかもしれません。
しかし、その人数要件についても今後引き下げられる予定となっており、令和9年10月に36人以上、11年10月に21人以上、14年10月に11人以上、17年10月で完全に廃止される見込みです。
負担軽減のため、厚労省は「年収の壁支援強化パッケージ」に取り組んでいますが、「キャリアアップ助成金」と「事業主の証明による一時的な収入増による加入義務の免除(連続2年まで)」のどちらも令和8年3月末までの時限措置であり、以降どうなるかは現状では未定(当然廃止もありうる)のため、長期的な対策とは言い難いです。
今後は“106万円の壁”が“20時間の壁”に移行することが予想され、年末の働き控えなどは依然として残るものと考えられます。
4.まとめ
ここまでの『年収の壁』を金額順に並べると次のようになります
①「106万円」 …社会保険の加入義務が生じる(撤廃予定)
※令和8年10月以降は“20時間の壁”
※現状、被保険者が51名以上の事業所のみ
②「110万円」 …本人に住民税の納税義務が生じる
③「123万円」 …扶養親族にできる上限(所得税・住民税)
※配偶者と特定親族は別
④「130万円」 …社会保険の扶養から外れる(従前のまま)
⑤「150万円」 …特定親族の満額控除ができる上限
⑥「160万円」 …本人に所得税の納税義務が生じる、かつ配偶者特別控除の満額控除ができる上限
⑦「188万円」 …特定親族控除が適用できる上限
⑧「201万円」 …配偶者特別控除が適用できる上限