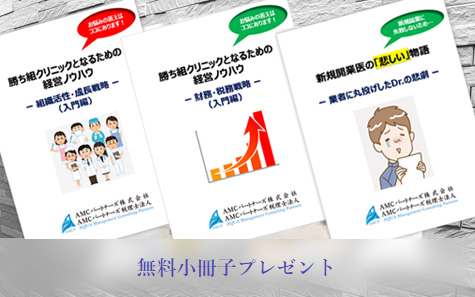生命保険金を受け取った際に税金がかかることがありますが、契約内容によって「所得税」であったり、「相続税」や「贈与税」であったり、はたまた非課税であったりと複雑多岐にわたり、頭を悩ませます。
そこで今回は、生命保険金にかかる税金の種類とその判別方法について解説して参ります。
1.基本的な考え方
生命保険金や給付金にかかる税金は、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって課税関係が変わってきます。難解に思えますが、考え方さえ理解してしまえば意外と単純です。
(1)契約者(保険料を支払う人)
(2)被保険者(保険金が支払われる理由となる人)
(3)受取人(保険金を受け取る人)
つまり、誰が保険料を支払って、なぜ保険金が支払われて、誰が保険金を受け取るのか、で判断するわけです。
なお、保険法上は「契約者」=「保険料負担者」ですが、必ずしもそうなっていないケースも相当数あります(後述)。さて、上記を踏まえての判断方法ですが、実は次の“3パターン”しかありません(所得税/相続税/贈与税)。
(1)契約者と受取人が同じ(所得税)
この場合、自分で保険料を支払い、かつ、自分で保険金を受け取ることで所得を得ているため、「所得税」がかかります。
(2)契約者と受取人が別(贈与税or相続税)
この場合、他の人が保険料を支払って形成した財産(保険金)を無償で受け取っているため、「贈与税」又は「相続税」がかかります。「贈与税」になるか「相続税」になるかは、被保険者が誰なのか、また、何故支払われたのか(保険事由)、によって決まります。
以上を踏まえて夫婦間でのパターンをまとめると次のようになります。
| 区分 | 契約者
(支払者) |
被保険者 | 受取人 | 保険
事由 |
税金 |
| 1 | 夫 | 夫 | 夫 | 満期 | 所得税 |
| 2 | 夫 | 夫 | 妻 | 満期 | 贈与税 |
| 3 | 夫死亡 | 相続税 | |||
| 4 | 夫 | 妻 | 妻 | 夫死亡 | 相続税 |
| 5 | 夫 | 妻 | 夫 | 満期 |
所得税 |
| 6 | 妻死亡 |
2.「所得税」がかかるケース
「契約者=受取人」のケースです(表1、5、6)。
主に、自己負担の養老保険の満期保険金の受取りなどが該当します。
受取方法は一時金と年金で選べることが多いですが、どちらにするかで所得税の計算方法が変わってきます。
一時金として受け取った場合は「一時所得」となり、50万円の特別控除と1/2課税の優遇が受けられます。
年金として受け取った場合は「雑所得」となり、総額は一時金より多くなる傾向にありますが、特別控除などの優遇は受けられません。
なお、解約返戻金については、基本的には契約者(負担者)に対して払い戻されるため、原則として「所得税」の対象となります。
3.「相続税」がかかるケース
「契約者≠受取人」で、かつ、保険事由が夫の死亡であるケースです(表3、4)。契約者(負担者)の死亡をトリガーに財産の移転が起こっているため、「相続税」の対象となります。
被保険者が夫の場合(表3)、一般的な死亡保険金となりますが、被保険者が妻(表4)の場合、正確には保険事由(妻の死亡)は発生しておらず、妻が取得したのは、夫が支払っていた保険を今後どうするか決める“権利(生命保険契約に関する権利)”になります。
なお、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、死亡保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)の適用が受けられます(“生命保険契約に関する権利”には適用はありません)。
4.「贈与税」がかかるケース
「契約者≠受取人」で、かつ、保険事由が満期であるケースです(表2)。契約者(負担者)が存命であり契約の満期をトリガーに財産の移転が起こっているため、「贈与税」の対象となります。主に他人負担の養老保険の満期保険金の受取りなどが該当します。
なお、暦年課税か相続時精算課税を選択しているかで課税額は変わってきますが、基礎控除110万円は共通なので、そこまでは贈与税がかかりません。
5.“名義保険”について
では、序盤に触れた「契約者」=「保険料負担者」が守られていないケースについてお話します。これは、いわゆる「名義保険」です。
よくあるのが、妻や子供を名義(契約者)にした養老保険や個人年金の保険料を実は夫が支払っていた、というケースです。
保険法上の扱いは上述の通りですが、税法上は実態(誰が負担したか)に対して課税がされます。そのため、最終的に保険金を受け取る人が本当の保険料負担者から“無償”で財産を受け取ったとして、「贈与税」の対象となります(保険事由が「保険料負担者の死亡」の場合は、死亡保険金等として「相続財産」になります)。
なお、解約返戻金は上述の通り、契約者に返金されるため、保険料負担者が違う場合は、こちらも「贈与税」の対象となります。
6.税金のかからない保険
最後に、次の保険金や給付金については税金が課されません。
・医療保険、がん保険、入院給付金
・高度障害保険金(一部例外あり)
・リビングニーズ特約(※)による生前給付金
これは、所得税法上、“病気やケガの治療のため”に支払われる保険金等については所得税が課されないこととなっているためです。
逆に言えば、上記以外の保険金や給付金を受け取った場合には、原則として何かしらの税金がかかることになります。
(※)リビングニーズ特約とは、医師に余命6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部又は全部を生前に受け取れる特約