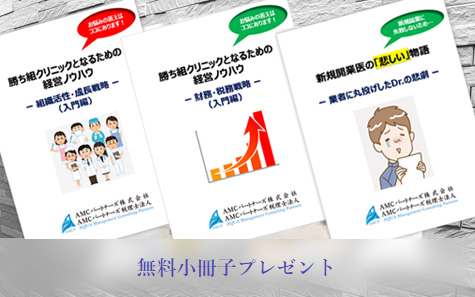今年の5月に『改正労働安全衛生法』が可決し、従業員が50人未満の事業所にも“ストレスチェック”を行うことが義務付けられましたが、皆様はご存知でしたでしょうか。
この法律は、実は既に平成27年12月1日に施行されており、その内容としては常時50人以上の労働者を使用する事業所が年1回のストレスチェックをしなければならないというものでしたが(50人以下の事業所は『努力義務』でした)、遂に、50人未満の事業所も義務化されてしまったのです。
但し、法律の施行日は「令和8年4月1日」ではあるものの、50人未満の事業所は産業医の選任義務がなく、実施するにも人的リソースが少なかったり、プライバシーの問題への配慮も必要であったり等の理由から、準備期間を設けるためにも施行期日は『公布後3年以内(最長で令和10年5月まで)に政令で定める日』とされ、現在、未だ具体的な施行期日が決まっていない状況です。しかし、施行期日が少し先になったとしても義務化されたことに変わりありませんので、準備は進めなければいけなくなったということです。
しかし、「経営で一杯一杯の中、スタッフのメンタルまでこちらが面倒見なければいけないのか?」「また意味のない事業主の労務関連の義務が増えた!」等、否定的な先生方が少なからずおられます。もちろん、お気持ちも十分に理解できますが、やはり義務化されなかったとしてもストレスチェックは事業所で取り組んだ方が良いと思われますので、今号では法律ができた背景も含め、その理由を解説させて頂きます。
【なぜ、ストレスチェック制度が義務化されたか?(背景)】
まず、きっかけとなった出来事は、昭和59年2月に日本で初めて過労による自殺が労災認定されたことで、これにより『メンタルヘルス対策』の重要性が叫ばれ、その後『精神障害による労災請求』が2000年には200件台であったものが、2015年には1,500件以上に激増し、加えて、20~30代という働き盛り世代の死因第1位が自殺という状況が続いたことから、制度的な対応が急務となり、まずは、2015年に労働安全衛生法を改正し常時50人以上の従業員がいる事業場に年に1回のストレスチェック実施を義務化し、従業員のメンタル不調を早期に把握し、うつ病等の一次予防(未然予防)を目指したということなのです。
尚、現在、法改正に基づき、人的リソースが少ない50人未満の事業所向けに、簡易な実施方法の策定やマニュアルの整備、産業医がいなくても外部委託等で対応が可能となるような調整が急ピッチで進められています。
【「義務だから」ではなく、「マネジメント」として必要な理由】
過去のAMCPレポートでも幾度か取り上げさせて頂いた職員の定着について、これまでであれば、院長と喧嘩をする、スタッフ同士で揉める等の「人間関係を原因とするもの」や、「給与・待遇を原因とするもの」と、分かりやすい退職理由が多かったのですが、昨今では、昨日まで「頑張ります!」と満面の笑みで言っていたスタッフが翌日から急に来なくなる等、理解し難い『サイレント退職』が蔓延しています。
サイレント退職とは、不満や悩みを1人で抱え、誰に相談することもなく自分1人で突然退職を決めて辞めてしまうことです。 スタッフとのコミュニケーションが重要であることは、かなり浸透したこともあり、各医院さんにて定期的にミーティングを開催したり、個別面談を行ったり、食事会等で親睦を深めたりされているところも増え、それなりに手応えを感じておられる先生も増えましたが、やはり、どうしても一定割合は、院長も先輩も、そのスタッフの親御さんでも全く兆候を読み取ることなく退職されてしまうケースが後を絶たないのです。
結局、これは、退職のハードルが下がっていることや、世代の違いもあるのですが、根本的なところ、本音(本心)を引き出せていないということで、今後は、いかに「スタッフが本音(本心)を出せる職場」になるかが重要なポイントになると思われます。そこで、それに活用できるのが“ストレスチェック”なのです。
【選択式の回答でも「本音」が出る可能性があるようです】
当然、ストレスチェックを導入するにしても、基本は、「本音を出しやすい環境」を作る工夫は欠かせません。本来であれば、「これは国で決まった義務ではあるが、当院では職員の健康のため職場環境改善に使用するので是非、前向きに協力して欲しい!」と熱意を持って説明すれば事足りるのですが、なかなか額面通りに受け取らないサイレント退職予備軍には、例えば、「どのような回答をしても、評価等に係るものではない」と不利益にならないことを担保したり、「誰が答えたか分からないようになっている」と徹底した匿名性を保証したりするだけでも、設問の選択肢に対して本音で回答する可能性は飛躍的に高まります。
これで、これまでになかった兆候を少しでも掴むことができるのであれば、義務だからと形式的に実施するのではなく、職員定着の為のツールとして活用しない手はないのでしょう。今後、義務化施行日に向けて準備を始められると思いますが、前向きな活用のためにも、是非、ご相談下さい。